
消費生活用製品安全法(消安法)施行を前にして、長く使うことによるトラブルを防ぐ生活用品の耐用年数が話題になっている。製品の製造や販売の規制とともに、適切な保守を促進したり、製品事故に関する情報の収集 及び提供等の措置を講じる法律である。
消費生活用製品安全法は、日本における製品の安全性を確保するための法律だ。
この法律は、消費者が安心して製品を使用できるように、製造業者や販売業者に対してさまざまな規制を設けている。
以下に、消費生活用製品安全法の主なポイントをまとめよう。
【対象製品】
消費生活用製品安全法は、消費者が直接使用するあらゆる製品を対象としています。これには、食品や医薬品、化粧品、家電製品、玩具、自動車、建築資材などが含まれる。
【製造業者の責務】
消費生活用製品安全法では、製造業者に対して以下の責務が課せられている。
・製品の安全性を確保するための十分な措置を講じること。
・製品の欠陥が発見された場合には、速やかに対応すること。
・製品の使用上の注意や警告を適切に表示すること。
・製品に関する情報を公開すること。
【販売業者の責務】
消費生活用製品安全法では、販売業者に対して以下の責務が課せられている。
・販売する製品が安全であることを確認すること。
・製品の欠陥や危険性について、消費者に適切な情報を提供すること。
・製品の使用上の注意や警告を適切に伝えること。
・販売した製品が欠陥品であることが判明した場合には、速やかに対応すること。
【検査・評価機関】
消費生活用製品安全法では、製品の安全性を検査・評価するための機関が設けられている。
これには、国立医薬品食品衛生研究所や国立医薬品食品衛生研究センターなどが含まれる。
【規制対象となる項目】
消費生活用製品安全法では、以下のような規制対象となる項目が設けられている。
消費生活用製品安全法で規制対象となる項目は以下のようになっている。
・有害物質の含有量
・電気製品の安全性
・医薬品・医療機器の安全性
・化粧品の成分・表示・表示方法の規制
・食品の表示・表示方法・添加物の規制
・玩具の安全性
・自動車・バイク・自転車の安全性
・燃料の安全性
・家庭用ガス器具の安全性
・タバコ・たばこ製品の規制
・建築資材の安全性
これらの規制対象項目について、消費生活用製品安全法は厳しい基準を設けており、安全性についての様々な要件が明確に規定されている。
製造業者や販売業者は、これらの要件に適合するよう製品を設計・製造・販売することが求められる。
また、消費者は、これらの要件に基づいて安全な製品を選択することができる。
といったことを踏まえた上で、以下をお読みいただけると幸甚である。
経済産業省に聞いてみた
昨今の大量生産、大量消費に疑問を感じている私は、物を大切に使うことを美徳と考えている。
たとえば、パソコンは2002年リリースのもの(Windows Me搭載マシンにWindows XPをインストール)もいまだに現役である。
外出時は、今流行のミニノートではなく、いわゆる青モバを使うこともある。
パソコンは、10年以上使おうと思えばそれも可能である。

が、だからといって、どんなものでも、とにかく長く使えばいいとは思っていない。
消費者にとって、性能が向上したものを使った方が効率も良く省エネルギーにもなるはずだ。
しかも、最近では安全性の問題が取り沙汰されている。
高齢者の住宅では、長年使っていた家電が老朽化で発火して焼死する事故も続発している。
そもそも物に「永遠」はない。耐用年数の範囲で、技術の発展に背かない程度のリプレイスが適当だと思われる。
では、現在使っている家電の耐用年数はいったいどうなっているのだろうか。
そう思った私は早速、関連団体やメーカーなどに話を聞いてみた。
まず、最初に私の理解を助けてくれたのは経済産業省である。
同省はこの問題について次の法律で対応することを説明してくれた。
「2009年4月1日に、改正消費生活用製品安全法(消安法)という法律が施行されます。これは、点検が容易でない製品として定められた特定保守製品と、電気用品安全法の技術上の基準で定められた、長期使用製品安全表示制度製品5品目(扇風機、換気扇、エアコン、洗濯機、ブラウン管テレビ)について、『設計標準使用期間』が定められたのです」
法律の文言はあいからずかたくるしい。さらに詳しくたずねると、「特定保守製品」というのは、ガス瞬間湯沸器、ガスふろがま、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機などのことを指すという。
そして、「設計標準使用期間」というのが「耐用年数」にあたるそうだ。
つまり、光熱関係の機器と、一般家庭への普及率が高い家電5品目について、安全に使える耐用年数や注意事項を製品本体に表示するよう、メーカーに義務付けるということである。
東芝に尋ねてみた
問題はそれが何年かということだが、最大手電機メーカー・東芝にたずねたところ、「具体的数値についてはこの施行に向かって工業会などで検討中の為、公表できる数値はまだございません」と前置きしながらも、「概ね10年程度を想定している」と教えてくれた。
今回の対象になっていない照明器具についても、同様に考えてよいという。
もちろん、10年たたなくても故障や挙動不審があれば、直ちに修理・メンテナンスは必要だが、とくに故障もなく通常の使い方なら、10年でリプレイスすることが健全な使い方ということである。
ちなみに同社からは、「補修用性能部品の保有期間」という参考資料をいただいたが、それによると、ラジオ、テープレコーダー、こたつ、パソコン、照明器具は6年、カラーテレビや電子レンジが8年、冷蔵庫が9年などとなっている。
同社はパソコンについても国際的なシェアを誇るメーカーである。
Windowsが圧倒的シェアを誇るパソコンは、OSのバージョンアップ時がリプレイス時と考える人が多いが、PCUNIXのようなパッケージでないOSを使う場合、パソコンの寿命に合わせて長く使うこともある。
その場合も、6年~10年が上限といったところだろうか。
自転車活用推進研究会に尋ねてみた
家電以外の生活用具では、自転車についても自転車活用推進研究会というところにお伺いした。
それによると、「ちゃんとした(価格なら10万円近い)ものは40年くらいは普通に使える」とのこと。
実際には2万円以下のいわゆるママチャリを使うユーザーがほとんどと思うが、その場合は2年程度、ひどいものは2ヶ月でガタが生じるものもあり、長く使うには整備が大切。
ただし、整備すら満足にできない粗悪品も出回っているのが現実という。
そうなると寿命以前に、まずは購入時に注意が必要ということか。
心配な方は量販店ではなく、自転車専門店で購入した方がいいかもしれない。
以上、消費生活用製品安全法(消安法)施行を前にして、長く使うことによるトラブルを防ぐ生活用品の耐用年数が話題になっている、でした。






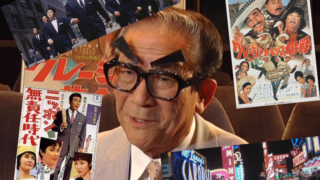














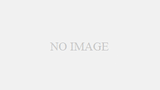

コメント