
松尾貴史先生が『日刊ゲンダイ』に連載している「統計データ怪析」が、回を追う毎にツッコミ所が目立ち読者を楽しませてくれている。9月17日付のお題は、「(理系卒ー文系卒)の平均年収」。中身は、「理系卒」の平均年収が「文系卒」よりも多いというデータをもとにいろいろ書いている。
連載によると、冒頭で、「理系=コミュニケーション能力に欠如しているというのは、単なるイメージでしかありません」と、いきなり筆者に(?)あてこすり(のつもり?)を一発。
この記事とは関係ないが天羽優子という人も、自分のブログで「私は法律だって凄いんだ」と気色ばみ、日頃の筆者のブログやメルマガに反論していた。
……と、書くと、事情を知らない方々は、何のことかと思われるので、簡単にご説明しよう。
私はジャパンスケプティクスの副会長だったが、ジャパンスケプティクスの役員には、物理学帝国主義を、むしろ自分から堂々と宣言する人がいて、どんな問題も「科学知識がないからダメだ」という結論にしていたので、それは会としてはダメでしょうと刃向かったら、私は副会長を解任(任期満了という建前)されて会を追い出された。
松田卓也という、会議の出席率が一番低かった人からは、「人を束ねる器ではない」と人格批判までされた。
ただそれでも私は一貫して、オカルト問題は物理学帝国主義では解決しません、と言い続けてきたのだが、それを受けて、ご両人の反論がそうだったということだ。
でも、繰り返すが、物理学帝国主義というのは、私が言ったことではなく、寿岳潤という役員が自ら言い出したことで、同じく役員だった心理学者の菊池総さんと言い争っていることも京都のシンポジウム(1998年)で実際にあったんだけどな。
機関紙掲載の校正の手紙のやり取りでも「続き」をやっていた。
菊池さんはいい迷惑だったと思う。
そういう事実もなかったことにする。とんだ「科学的」だ。
それどころか、「事実である方」ではなく、物理学者の味方になった方が得策だと考えた、松尾貴史さんや天羽優子さんが、私の悪口を書いているということなのだろうと思う。
ただ、天羽優子さんは、ブログでは堂々と私を名指ししているので、その「フェア」な精神だけは認めよう。
一方、松尾貴史さんは、草野直樹ごとき無名のB層は、いちいち名前を挙げて批判するだけの存在ではない、ということで、名前すら出さずにあてこする二重の侮辱をしている。
あ、ちなみに松尾貴史さん、紀藤正樹さん、加門正一さんを、ジャパンスケプティクスの役員に推薦したのは私なんだけど、言うなれば、松尾貴史さんは恩知らずということです。
松尾貴史さんは、立ち位置で物を言う人というイメージがますますかたまってしまった。職業用のスケプティクス。

いずれにしても、人は信用しないこと、という教訓を得ました。
それ、矛盾だらけですよ
それはともかく、松尾貴史先生のその後の文章はいただけない。
こういう書き物をしているようではさぞ忙殺されているんだろうな、と思う。
松尾貴史さんによると、理系は、芸術や娯楽などを学校時代に排除した生活をしていても、より多い収入があるから、その後は年を追うごとにそれらを身につけられると楽天的に書いている。
そして、「収入の少ない文系」はその点で理系に差を付けられるから「おいたわしい話」などと挑発的に書いて悦に入っている。
松尾貴史サン
あんた、いつから理系になったの?
というツッコミはさておき、
「収入が多い」からといって、それらを身につけられる「余暇」「余裕」があるかどうかは全く別の話だろう。
世の中で、もまれている人なら、「収入が多い」ということは、本来ならそれだけ「働かされている」と疑うのが普通だ。
つまり、データの平均収入を引き上げている人たちは、より多くの収入と引き替えに、より多くの労働をさせられることによって、松尾貴史さんの考察とは正反対に、むしろ芸術や娯楽などを楽しむ時間と心の余裕を奪われているかもしれない、と心配するものだ。
たとえば、医師や技術者などの過酷な労働を、認識していないのか。
彼らの悲鳴が聞こえてこないのか。
それを考慮できない松尾貴史先生のセンスこそが、浮き世離れした「おいたわしい話」なのである。
まあ、松尾貴史さんの人生観では、「カネ」が全てを解決できるのかもしれないが、一般の人が、この社会の中で一歯車として生きていくということは、それほど単純なことではない。
だいたい、そのデータの「収入が多い」というのは、あくまで就職できた人の話だろう。
就職できた人がいくらか高いお給料をもらっていたとしても、就職できていない人はどうなのだろうか。
「平均」の収入を見て何が語れるのだろう。
今の世の中、どれだけ格差があると思っているのか。
昨今の就職難と、社会の高度化・複雑化で、理系・文系固有の職域がかなりボーダレス化していることも見るべきである。
出てきた数字の背景は「文系」「理系」で切れるような単純なものではないかもしれない。
いずれにしても、もとになるデータそのものにツッコミ所が多々ありそうということだ。
その程度の統計なのである。
だが少なくとも、松尾貴史先生の文章から、筆者が指摘するような懐疑、とりわけ、理系労働者の苦悩に対する配慮は全くなかった。
松尾貴史さんは、スケプティクスなセンスが足りないと思う。
何よりおかしいのは、一見、理系の人々の側に立っているようでいて、実はそうではない冷たさを感じる文章である。
上司は理系だったけどな……
筆者の体験談で恐縮だが、筆者は日本で一番大きいといわれる保険会社に入ったことがある。
当然高収入だ。収入も日本一ではないだろうか。
では、その会社の人たちが、「普通」のサラリーマン以上に芸術や娯楽などを楽しんだかというと、見ている限りそんなことはなかったなあ。
高収入に見合う労働に明け暮れたからだ。
そして、大きい会社ほど競争も激しいから、風呂敷残業も自主的に行った。
「高収入」の少なくない部分は、疲労解消のマッサージ代や自主学習などに費やされていた。
むしろ、「芸術や娯楽などの時間」を取りたい人は会社を辞めて、文系だの理系だのに関係なく何でもやらなければならない零細の自営に転出するしかなかった。
大きい会社というのは、あらゆるセクションをもっているから文系も理系も入る。
文系が理系の職域に回るケースは少ないかもしれないが、いろいろな理由から逆は有り得る。
たとえば、管理工学や建築学専攻の人が営業支社に回ることもある。
筆者の上司も理系だった。
慶応の管理工学だったかな。大学院まで行ったかどうかは定かでないけど。
転勤、異動が容赦ない上場大企業に入ると、文系対理系という、松尾貴史先生がたてた対立軸自体が、一面的なものでしかないのでは?と思う。
松尾貴史先生のホームグラウンドである芸能界は裁量労働の世界であり、賃金と労働時間がおおむねリンクする一般の労働者とは根本的に異なる。
松尾貴史先生は、労働者のことなど全くわからないのだろう。
失礼ながら、今回はそうした先生の認識の欠如がもたらした「怪析」であると思うがどうだろうか。
みなさんも『日刊ゲンダイ』の松尾貴史先生の連載をお読みになっていろいろ考えて欲しい。

見所、ツッコミ所がたくさんある。
毎週木曜日発売分に掲載されている。
以上、松尾貴史さんが『日刊ゲンダイ』に連載する「統計データ怪析」が回を追う毎にツッコミ所が目立ち読者を楽しませてくれる。でした。














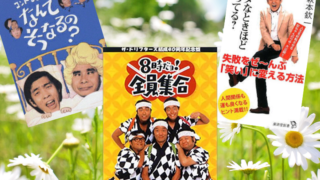






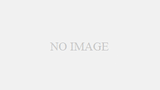
コメント