
とうもろこしは、野菜としてだけでなく穀物や飼料としても使われる汎用性の高い食材。その品種や選び方、栄養素についてご紹介しよう。とうもろこしは、さまざまな食品加工技術によって、缶詰やジュース、スナック菓子などに幅広く利用されている。
とうもろこしについて、まず簡単にご紹介しておこう。
とうもろこしは、北アメリカ原産の穀物で、世界中で広く栽培されている重要な食用作物の一つ。
一般的に、トウモロコシと表記される。
とうもろこしは、炭水化物やタンパク質、ビタミン、ミネラルなどの栄養素を含んでいる。
また、特に黄色いとうもろこしには、β-カロテンという抗酸化物質が含まれており、免疫力を向上させる効果があるとされている。
また、とうもろこしには、消化器官を刺激する食物繊維が含まれており、便秘の改善に役立つことが知られている。
さらに、とうもろこしは、さまざまな食品加工技術によって、缶詰やジュース、スナック菓子などに加工されることがある。
というと、いい事尽くめの食材のようにも感じる。
とうもろこしについては、ポリコーンという、ジャイアントコーンを使ったお菓子をご紹介したこともある。
ポリコーン(坂金製菓)はジャイアントコーンというトウモロコシを膨張させイソマルトオリゴ糖の甘く軽い味がついたお菓子 #トレンド雑談 https://t.co/DQn1fjpPnn
— 赤べコム (@akabecom) March 19, 2023
一方、とうもろこしには、アレルギーを引き起こす可能性があるとされています。
特に、とうもろこしタンパク質に対してアレルギー反応を示す人がいることが知られています。
以上のことをお含みおきの上、とうもろこしについて以下の記事をお読みいただけると幸甚である。
とうもろこしの進化
とうもろこしの進化、品種、選び方、栄養成分などについて書こう。
夏の風物詩であるとうもろこしは、鍋に水を入れ、皮をむいて塩と一緒に入れ火にかける。湯が沸いて数分たったら黄色い実の色が濃くなり、つやつやと光ってきたらざるにあける。
この時立ちのぼる湯気と独特の香りに、私はいつも夏の到来を感じている。
そんなときのとうもろこしは、スケプティクスになる必要なく、おいしい。
ゆでてよし、焼いてよし、サラダにスープに炊き込みご飯、さらにはお菓子まで、幅広く使われているとうもろこしだが、野菜として市民権を得たのは意外と遅く、昭和30年代だったようだ。
とうもろこしにはさまざまな品種があるが、最初に日本に持ち込まれたのはフリントコーンと言われるもので、あまり美味しいものではなく、家畜の餌として栽培されていたという。
そのあと、甘みのあるスイートコーン種の中でも甘みが強く栽培しやすいゴールデンクロスバンタム種がアメリカから導入され、採種体制が確立された昭和30年代中ごろから野菜として普及し始めたとされる。
昭和40年代に入ると、ハニーバンタムに代表されるスーパースイート種が輸入され、とうもろこしの人気は不動のものとなっていく。
私が子どもの頃はとうもろこしといえば、このハニーバンタムが主流だったように思うが、いつのまにかスーパーで見かけるのはピーターコーンばかりになり、気がついたらそれも消えて味来なんていう品種が並ぶようになっていた。
一体何種類のとうもろこしがあるのだろうと思っていたら、年々品種改良が進められ、より高糖度で食べやすいものが作られているのだという。
ちなみに、現在販売されている品種は、味来(みらい)、恵味(めぐみ)、ピクニックコーン、ゴールドラッシュ、ピュアホワイト、ミエルコーンなどなど……。
これらの品種はもちろんどれも甘いのだが、それ以外にもそれぞれに特徴がある。
たとえば、恵味は味来を品種改良したもので、味来に比べて実や皮が柔らかい。すっきりとした甘さを持ち、その甘みの低下が遅いため、収穫後ある程度時間が経っても美味しく食べられる。
ピクニックコーンは小ぶりで家庭用の鍋でも調理しやすく、少人数の家庭でも使いやすい。また、「冷たくされると甘いんです」のキャッチフレーズ通り、冷やして食べると美味しさがひきたつ。
茹でるか電子レンジで加熱したものを氷水にさらして手早く冷やし、ラップにくるんで冷蔵庫で保管すると3日程度はプリプリした食感が保てるという。
ゴールドラッシュは単に甘いだけでなく食味がよいと評判の品種。皮がとても柔らかく、歯にひっかかったり口の中に残ったりしにくいので食べやすい。早生種のためいくぶん小ぶりながらも、先端不稔がなく、安定した大きさで収穫できるとされる。
ピュアホワイトはその名の通り真っ白な粒の色とクリーミーな甘さが特徴。メロンと同等の糖度を持ち、フルーツ感覚で生食が可能である。
ミエルコーンはとうもろこしの中でもずばぬけた甘さを誇る品種で、市場にはまだあまり出回っていないため、ギフト用としても人気が高い。
ちなみに「ミエル」とはフランス語で「蜂蜜のような甘さ」の意味だというから、その糖度の高さは推して知るべし。これも生食可能な品種だ。
こうしてみると、どれも甲乙つけがたい魅力を感じる。
共通しているのは、高糖度で皮が柔らかく食べやすいという点のようだ。
しかし、いくら品種改良が進んでも、新鮮なものを新鮮なうちに食べなければせっかくの美味しさも半減してしまう。
とうもろこしの選び方
そこで店頭におけるとうもろこしの選び方だが、毛が褐色または黒褐色で葉の緑が濃いものがいい。毛の色が濃いのは完熟している証拠であり、葉の緑の濃いのは新鮮だからだ。
そして買ってきたらすぐに茹でること。
ラップにくるんで電子レンジで加熱してもよい。
とにかく早く調理することだ。すぐに食べない場合は冷凍保存しておけばよい。
やむなく生のまま保存する際は、冷蔵庫の野菜ボックスに皮付きのまま立てておく。とうもろこしは自分で天に向かって立つ性質があり、寝かせておくと立とうとして自らの糖分を使ってしまうのだそうだ。
このため、一晩寝かせたとうもろこしと、立てて保存したものとでは、糖分に差がついてしまうのだという。
とうもろこしのおもな栄養成分は炭水化物。
カロリーが高く、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンEのほか、銅、亜鉛、マグネシウムなどのミネラルも含まれている。
エネルギーを補給し、身体の調子を整える効果が期待できるため、夏ばて解消にはうってつけだ。
とうもろこしの旬は7月から9月にかけての2ヶ月あまり。
美味しい品種を研究開発してくれた種苗会社と、栽培・収穫に汗を流してくれた農家の皆さんに感謝しながら、たくさんとうもろこしを食べてこの残暑を乗り切りたい。
以上、とうもろこしは、野菜としてだけでなく穀物や飼料としても使われる汎用性の高い食材。その品種や選び方、栄養素についてご紹介、でした。
















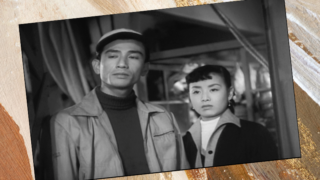






コメント